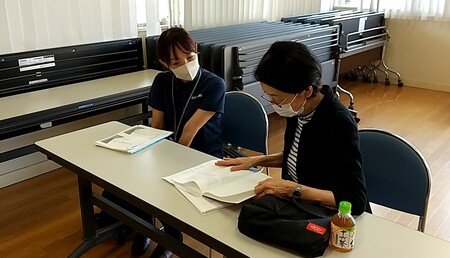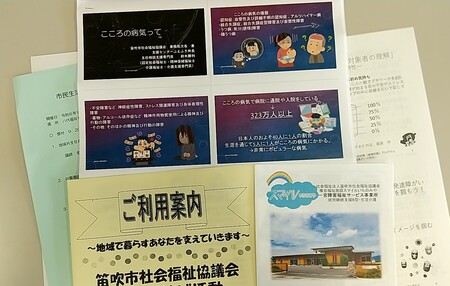![]() 梅雨の晴れ間、6月29日に「生活支援員・市民後見人養成講座フォ ローアップ研修会」をスコレーセンターにて開催いたしました。今日は、この研修会の様子を少し紹介いたします。
梅雨の晴れ間、6月29日に「生活支援員・市民後見人養成講座フォ ローアップ研修会」をスコレーセンターにて開催いたしました。今日は、この研修会の様子を少し紹介いたします。
前回2月は、市民で守る高齢者・障害者の権利と題しノーマライ ゼーション、自己決定の尊重、現有(残存)能力の活用を学びましたが、今回は、これを具体的に実現する為の「人権と権利について」理解を深める機会となりました。
講師は、前回2月の講座で大好評だった河西社会福祉士事務所の河西俊文先生に引き続き依頼しました。解説は池上彰さんのように分かりやすく、「人権について」考える視点が大切であることを学びました。
![]() 講義「育てようかけがえのない一 人ひとりの人権」
講義「育てようかけがえのない一 人ひとりの人権」
![]() 人権を考える3つの視点
人権を考える3つの視点
1.人としての問題なのか?
すべての人が生まれながらにして持っていて、他人がどのような 理由によっても奪うことのできない固有の権利
→例:認知症高齢者だから、障害者だから・・・
2.人と人との問題なのか?
全ての人の人権を同時に守る事は簡単ではない
→例:信号の無い交差点 *人権と人権の衝突
3.社会・地域の問題なのか?
市場経済発展→貧富の差、社会不安→多数の失業者![]() 茶話会
茶話会
以前アンケートで、受講者の交流の場を求める声が寄せられていたので、今回は研修の休憩時間を茶話会として20分、ほっと一息つきながら皆さん会話を楽しまれていました。カロリー1/2のカフェオレが人気でした![]()
![]() グループワーク「人間としての平等と尊厳」
グループワーク「人間としての平等と尊厳」
今回は、同じ国で同じ日に生まれた2人の赤ちゃん(一人は宮殿の中、もう一人は貧しい小屋の中)の事例を通して、アジサイチームとカタツムリチームに分かれて話し合いました。
1.かけがえのない存在として尊重される人は?それはどうしてか?
2.あまり尊重されない存在とは?それはどうしてか?
3.なぜ全て等しくかけがえのない存在として尊重される権利があるのか?
と言った問いを皆さんで考えてみました。
![]() 「視点として」河西先生の総括より
「視点として」河西先生の総括より
*人の属性や環境を取り払って本人を見る目が必要である。
宮殿の中と貧しい小屋の中で生まれた子は→将来もこのまま同じとは限らない。
自由権・平等権→その人自身の考え方、生き方で変わる。家柄、財産、職業、国籍、民族などによって判断されない「裸の個人」として本人の気持ちを知ることができる。![]() アンケート結果
アンケート結果
講座の内容、全体のバランス共に良い評価をいただきました。
また、今回も多くの気づきを皆さんからいただいています。
詳しくはこちらをクリック → フォローアップ研修アンケート.pdf
![]() 担当より
担当より
皆さんから出していただいた意見(アンケートの気づき)にあるように「人権」について改めて考えたり、振り返ったりすることが大切だと実感した研修となりました。
![]() 今後の予定
今後の予定
*平成24年度の生活支援員・市民後見人養成講座は、11月上旬に3日間で開催予定。
*フォローアップ研修会は2月を予定しています。
この研修会は、笛吹市高齢福祉課から市民後見人養成講座の委託を受け、養成講座受講者への継続研修を目的として昨年度から開催しています。
W=hagi、P=huji
問い合わせ
笛吹市社会福祉協議会 後見センターふえふき
tel 055-263-5855