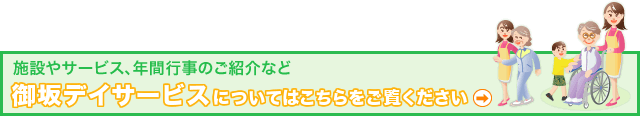このところ毎日猛暑続きです![]()
暑くて溶けちゃいそうですね![]()
![]()
御坂通所では7月に七夕会![]() を行い、
を行い、
天下茶屋へ野外レクに行って来ました![]()
![]()
7月7日 七夕会


↑
今年も御坂通所に織姫と彦星が舞い降りました(笑)



七夕の由来について
「棚機(たなばた)」とは古い日本の禊ぎ(みそぎ)行事で、乙女が着物を織って棚にそなえ、神さまを迎えて秋の豊作を祈ったり人々のけがれをはらうというものでした。
選ばれた乙女は「棚機女(たなばたつめ)」と呼ばれ、川などの清い水辺にある機屋(はたや)にこもって神さまのために心をこめて着物を織ります。そのときに使われたのが「棚機」(たなばた)という織り機です。
やがて仏教が伝わると、この行事はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになりました。現在七夕という二文字で「たなばた」と当て字で読んでいるのも、ここから来ていると言われています。
選ばれた乙女は「棚機女(たなばたつめ)」と呼ばれ、川などの清い水辺にある機屋(はたや)にこもって神さまのために心をこめて着物を織ります。そのときに使われたのが「棚機」(たなばた)という織り機です。
やがて仏教が伝わると、この行事はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになりました。現在七夕という二文字で「たなばた」と当て字で読んでいるのも、ここから来ていると言われています。
織姫と彦星について
琴座のベガと呼ばれる織女(しゅくじょ)星は裁縫の仕事、鷲(わし)座のアルタイルと呼ばれる牽牛(けんぎゅう)星は農業の仕事をつかさどる星と考えられていました。この二つの星は旧暦7月7日に天の川をはさんで最も光り輝いているように見えることから、中国でこの日を一年一度のめぐりあいの日と考え、七夕ストーリーが生まれました。
![]() 天下茶屋に行って来ました
天下茶屋に行って来ました![]()
太宰治の『富嶽百景』の一節にある【富士には月見草がよく似合う】の舞台となっている河口湖町の天下茶屋に行って参りました。
月見草はまだ咲いていなかった為、富士山を見ながらお茶を飲む事にしました・・・が、










連日、雲がかかっていて一度も富士山を拝む事が出来ませんでした。


晴れていると富士山がよく見えます。
≪裁縫近況報告≫
雑巾ミッションの続きです
この1ヶ月ほどで30枚近く進み、
残り30枚となりました!!
とてもペースが早いです!!

御坂通所介護事業所:林