笛吹市自立支援協議会相談支援部会では、昨年に続いて障がい者虐待の研修を開催しました。
これは、笛吹市内の相談支援に関わる支援関係者を対象にした研修会です。昨年も弁護士の高橋由美先生に講師をお願いしていますが、事例を元にした講義のため、参加者にはとても分かりやすいと好評でした。

障がい者(児)に対する「虐待」は、「障がい者に対する不適切な言動や障がい者自身の心を傷つけるものから傷害罪等の犯罪となるものまで幅広いもの」と考えられています。 障がい者の虐待防止を考える際は、家庭内虐待に対しては虐待を受けた者と虐待を行ってしまった家族等の双方への支援を位置づけることが求められます。また、施設内虐待に対しては「訓練」や「指導」の名のもとにおける虐待を見逃さないことが必要です。
また、障がい者の一般の会社や福祉施設での就労が進む一方、雇用側の力関係による虐待も増えています。
いずれにしても、効果的な虐待防止ためには、関わる職員の知識とスキルの向上が必要で、お互いの傷が深くならない内の早期発見、早期対応が重要です。

後半は、事例を用いての演習です。障がいのあるAさんには同居する高齢の両親と兄弟がいますが、いずれも様々な生活課題を抱え、寄り添いながら生活をしています。しかし、高齢の両親も介護が必要な状態になったり、兄弟にも病気がある可能性があり、就労が難しいなどの課題があります。
Aさんは満足な介護も受けられず、自身が受給している年金も生活費に消えてしまう・・
さて、これは虐待に当たるのでしょうか。

この事例を元に、参加者は3つのグループに別れ、協議します。


誰が誰に対してどのようなことが起きているのか。それは果たして虐待に当たるのだろうか。
虐待ならば、我々はどのようなことをすればいいのか。そして、誰をどのように支援すればこの状態が改善するのか。
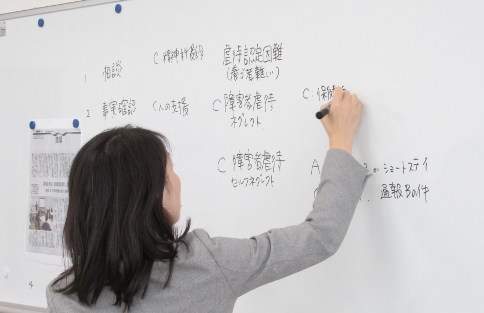
各グループで話し合った結果を皆で共有します。
この家族で起きた事件から、虐待の種類やどのような対応をすべきなのかを明確にしていく作業です。特に高橋弁護士は「権利擁護」という視点での介入を説明しました。暴力的な行為が少ないとしても、また家族に様々な課題があるとしても、Aさんが自立して生きていく権利は守られるべきであり、高齢の両親にも「高齢者虐待」の可能性という視点を入れて考えるという複合的な思考が大事だと説明がありました。
障害者虐待防止法では、次のように定めています。「国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課す。」
早期発見・早期対応が障がい者の権利を守る第一歩です。そのためには、福祉に関わる職員が常にアンテナを高くし、虐待を発見する目を育て、市町村への通報を行うことです。
今後も障害者虐待防止法や障害者差別解消法などの法律・制度は、障がい者の権利擁護には大事なツール(道具)です。今後も学習会を行う予定ですので、関係者の皆様の多くの参加をお願いします。また、相談支援部会は2ヶ月に1回、事例検討会を行っていますので、そちらにも参加をお願いします。
鈴木勝利














