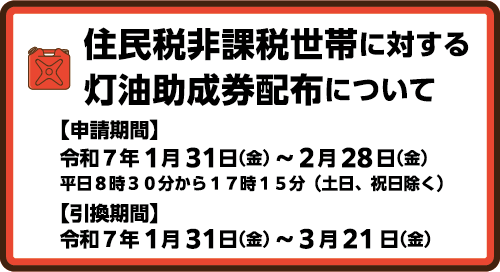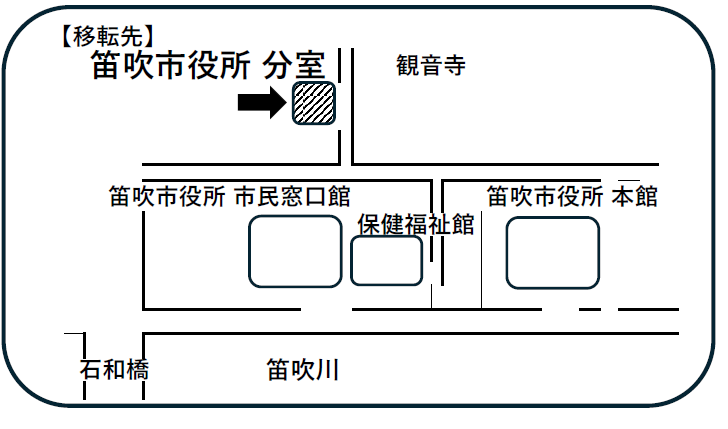石和西小学校4年生の授業で福祉講話が行われました
 お話させていただいた内容の概要
お話させていただいた内容の概要
 「ふくし」とは
「ふくし」とは  「福」=幸運 「祉」=神の恵み、さいわい 「福祉」=しあわせ
「福」=幸運 「祉」=神の恵み、さいわい 「福祉」=しあわせ  「ふくし」=ふだんの くらしの しあわせ
「ふくし」=ふだんの くらしの しあわせ 幸せは人によってそれぞれ違う。 でも、同じこともある。
幸せは人によってそれぞれ違う。 でも、同じこともある。 人は一人ひとりちがう。でもみんな同じ「人間」
人は一人ひとりちがう。でもみんな同じ「人間」 みんなが生活しやすいよう、いろいろな「ふくし」がある
みんなが生活しやすいよう、いろいろな「ふくし」がある 「ふだんの くらしの しあわせ」とは、自分や周りの人のそれぞれが感じる「幸せ」をみんなでつくっていくこと
「ふだんの くらしの しあわせ」とは、自分や周りの人のそれぞれが感じる「幸せ」をみんなでつくっていくこと 「ふくし」のたとえば(車いすマーク/耳マーク/マタニティマーク/点字 などなど)
「ふくし」のたとえば(車いすマーク/耳マーク/マタニティマーク/点字 などなど) ふくしクイズ
ふくしクイズ
 講師
講師 スズキブレース 鈴木様、佐々木様
スズキブレース 鈴木様、佐々木様

 主な講話内容
主な講話内容
 義肢(義手、義足)は手および足を失っている方が使用する
義肢(義手、義足)は手および足を失っている方が使用する 装具は手や足の機能を補完するために手や足に装着する
装具は手や足の機能を補完するために手や足に装着する 義肢、装具は早くつけるほど良い(自分の体になれる)
義肢、装具は早くつけるほど良い(自分の体になれる) 子どもの義肢は成長に応じて数ヶ月から半年ごとに作りかえる
子どもの義肢は成長に応じて数ヶ月から半年ごとに作りかえる




 障害のある方等に接する時は、友達に接するように接してほしい
障害のある方等に接する時は、友達に接するように接してほしい ふだんしていること(友人に優しくする等)が福祉
ふだんしていること(友人に優しくする等)が福祉
石和西小学校4年生は1学期、「福祉」の中でも自分の関心のあること(視覚障害、聴覚障害、義手 等)について調べ学習を行ってきました。
2学期は当事者の方や支援者の方の福祉講話です これは実際にお話を伺う事で、1学期に調べた事との関連を考えて学びを深めることが目的です
これは実際にお話を伺う事で、1学期に調べた事との関連を考えて学びを深めることが目的です
福祉講話は11月16日と12月18日の2回に分けて行われました
今回は11月16日に行われた「身の回りの福祉について」「義肢装具士による講話」についてご紹介します
初めに社会福祉協議会石和地域事務所職員・霜鳥より「身の回りの福祉について」という題で「ふくし」についてのお話をさせていただきました
Q.通信手段の1つで、耳の不自由な人にとって電話の代わりになるものは? A.ファックス などなど
その後、義肢装具士のお2人より、義手義足や装具についてお話をいただきました
児童達は、1学期の調べ学習では義手義足に関する資料が少なかったこともあり、時々質問しながら熱心に聞いていました

義肢装具士とは・・・
義肢装具士は法律上、「医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と定められ、医師の処方に従い患者さんの採型や採寸を行い、これを元に義肢装具を製作して、病院などで適合を行います。また患者様が快適に過ごせるように、不具合があれば原因を突き止め、調整を繰り返し、最終的に適合した義肢装具を提供します。
義手・装具を持参してくださり、分かりやすく講話してくださいました

(鈴木様は生後10ヶ月のお子さんに義足を作った事もあるそうです)
義肢や装具を触ってみました
本物の手と見分けがつかない


ちなみにこちらの服を着ていない手が義手です ▼▼拡大写真▼▼

休み時間中も、義手や装具を間近で見たり触ったり・・・
講師の先生の周りには人だかりができていました

鈴木ブレース様では車いすも取り扱っているとのことで、車いすの種類等もご説明してくださいました

最後に鈴木様よりまとめのお話
これまでたくさんの患者様と接し、また鈴木様ご自身も装具ユーザーであり、それも含めてたくさんのお話をしていただき、深い学びができた福祉講話でした
2回目の福祉講話(12月16日、視覚障害、聴覚障害当事者の方による講話)の様子はまた次の機会にご紹介させていただきます

福祉教育推進事業
福祉教育やボランティア体験などを通じて、いのちの大切さを学び、児童・生徒の福祉のこころを醸成する事を目的として、笛吹市内の小中高等学校を「福祉教育推進校」として指定して、社会福祉協議会より55,000円を上限として福祉教育に関する費用を助成する事業です。
助成金の財源は市民や法人の皆様からご協力いただいた、社会福祉協議会の会費が充てられています。
今回社会福祉協議会では、福祉講話「身の回りの福祉について」の講師を務めさせていただくとともに、義肢装具士(福祉講話講師)の調整をさせていただきました。
こんなまちであったらいいな 安心して暮らせる幸せあふれるまちづくり
つなげよう、つたえていこう、温かい心 いさわ
石和地域事務所 霜鳥