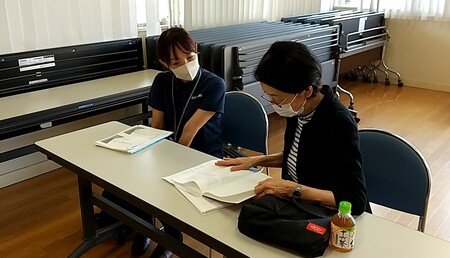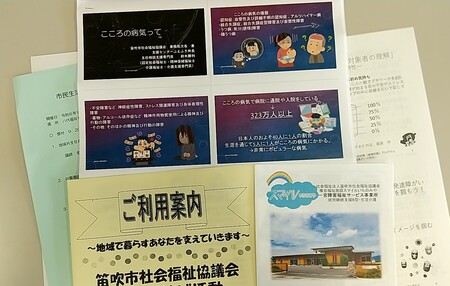|
生活支援員・市民後見人養成フォローアップ研修を2月14日に開催しました!
13名の市民の方(現場研修修了者・市民生活支援員・市民後見人)が参加してくださいました ありがとうございました ありがとうございました
今回の研修会では意思決定支援について相談支援専門員、後見人の立場からの発表を聞き、意思決定支援とはどのような過程を踏み、どんな視点を持って支援を行うものなのかを知ることを目的としました
発表者は服部敏寛 相談支援専門員(社会福祉法人三富福祉会サポートセンターハロハロ)と宮沢秀一 社会福祉士(福祉後見事務所ほたり)です。

服部さんからは・・・
「障がい者の意思決定支援への配慮は法律的に義務付けられている。本人が主役となり、自分で決定することが出来るような支援をすること、その人のもつ文化を大事にしながら、自由の制限が少ない選択肢を見つけることが大切である。相談支援専門員としては本人の強みを見出し、言葉にならない行動や思いを言葉にしていくことを心掛け、未来を見据えた支援を行っている、意思決定のためのプロセスを重視している。良質な意思決定支援を支えることができる地域は誰もが住みやすい地域となる。」

宮沢さんからは「本人との信頼関係の構築が必要。地域で生活したい、暮らしたい思いを支える、本人だけでは出来ないことに手を差し伸べる、社会の一員として共に暮らせる支援をする。常に本人が中心にいるなかでの方向性を決めていくための支援者間の意思合意形成も必要。本人が意思を表明しやすいように本人と一緒に考える姿勢をもつ。じっくりと本人の意思決定を待つことが大切。」
との内容をわかりやすく受講した市民の方々へ伝えていただきました

発表のあとはグループワークのなかで発表を聞いて感じたこと、考えたことを話し合っていただきました。
|
・本人との信頼関係を築くためには時間をかけることが必要。
・意思決定支援はチームで話し合う。これからの支援に勉強になった。
・継続して勉強することが大切。
・意思決定支援を行う際にどのようにしているのか事例を教えて欲しい。
・支援をしている時本人の意思が表現できた時はホットする。難しい問題だが やりながら学んでいくものだと思う。
などなど・・・
今回の研修で学んだことを今後の生活支援員・市民後見人の実践活動のなかで活かしていただけたらと思います
後見センター 今泉
|
|