一宮中学校の1学年総合的な学習において
2月8日(金)と2月15日(金)の二週に渡り、「福祉体験」と「福祉講話」の授業が行われました。
まずは、2月8日(金)の「福祉体験」をご紹介します![]()
「福祉体験」では、高齢者や障がい者の状況や心情を理解すること、
介助の必要性や難しさについて考え、感謝や思いやりの気持ちをもつことを目的に
車いす体験、アイマスク・白杖体験、高齢者疑似体験が行われました。
3つすべてを体験できるよう各グループごとに分かれ、それぞれ回り体験しました![]()
![]() 車いす体験
車いす体験
体験者・介助者を交互に行い、車いすに乗り、坂道・段差等を通り、乗った感じや操作の仕方などを学び、また水道など普段使っている所を車いすで行うとどんな難しさがあるかを体験しました。
![]() 「手は届くけど、水は飲むことができない」と大変さを実感・・・
「手は届くけど、水は飲むことができない」と大変さを実感・・・
![]() 段差を体感 「介助をするって大変なんだな」
段差を体感 「介助をするって大変なんだな」
![]() アイマスク・白杖体験
アイマスク・白杖体験
体験者・介助者を交互に行い、視覚障がいのある方にとって目の役割をしている白杖を体験し、介助 の仕方、注意点等を学び、どのような声かけ、支援があったらいいかを考えながら体験に臨みました。
![]() 「階段を上るより下りるほうが怖い」と話していた生徒が多くいました。
「階段を上るより下りるほうが怖い」と話していた生徒が多くいました。
「あと一段で上り終わるよ」「障害物があるから気をつけて」と声をかけながら、介助にあたっていました![]()
![]() 高齢者疑似体験
高齢者疑似体験
高齢者疑似体験にあたり、山梨県介護普及実習センターの河嵜様に講師を依頼し、装着の仕方、注意点等を教えていただきました。また、地域のボランティアの箸本様にもご協力いただきました![]()
![]() 講師に教えていただきながら、みんなで装着していきました。
講師に教えていただきながら、みんなで装着していきました。
![]() ゴーグルを装着して読書「いつもより見えにくいな」
ゴーグルを装着して読書「いつもより見えにくいな」
普段見慣れた学校の風景が体験を通してどのように変わったでしょうか。
![]() 「高齢者の体験をして、自分のおじいちゃん、おばあちゃんがどういう状況なのか分かり
今回体験をして二人を支えていこうと思えた」
「高齢者の体験をして、自分のおじいちゃん、おばあちゃんがどういう状況なのか分かり
今回体験をして二人を支えていこうと思えた」
![]() 「高齢者体験では思った以上に体が動かずびっくりした」
「高齢者体験では思った以上に体が動かずびっくりした」
![]() 「車いすやアイマスクの介助がとても難しかった」
「車いすやアイマスクの介助がとても難しかった」
![]() 「介助するとき、相手が怪我をしないように気を配った」
「介助するとき、相手が怪我をしないように気を配った」
などなど、たくさんの感想がありました![]()
インフルエンザのため、体験できなかったクラスがありましたが、福祉体験を通して、さまざまな人の「ちがい」を理解することができたのではないでしょうか。
次回は福祉講話についてご紹介します![]()
【福祉教育推進事業】
福祉教育やボランティア体験などを通して、いのちの大切さを学び、児童・生徒の福祉のこころを醸成することを目的として、笛吹市内の小中高等学校を「福祉教育推進校」と指定して、社会福祉協議会より55,000円を上限として福祉教育に関する費用を助成する事業です。 助成の財源は市民や法人の皆様からご協力いただいた社会福祉協議会の会費が充てられています。










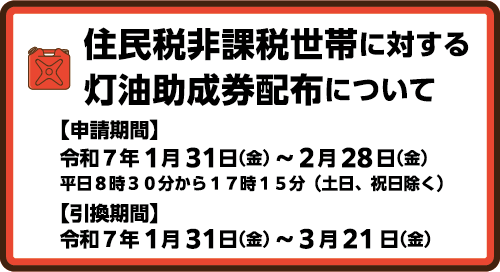
-thumb-800x1126-21926.png)


