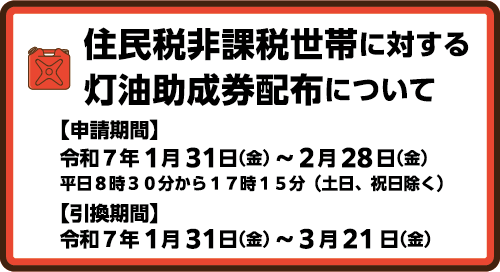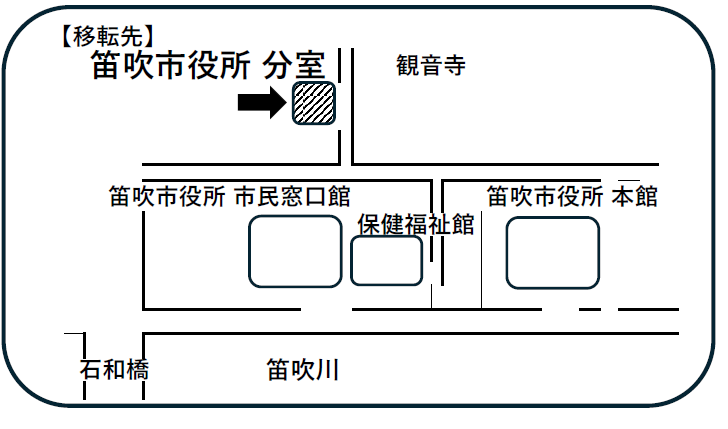笛吹川を元気に泳ぐアユの姿に歓喜!
5月20日に石和南小学校の4年生が、笛吹川の河川敷でアユの稚魚の放流体験をしました。
この放流体験は、日本釣振興会山梨支部が企画し、地域の子どもたちに魚のことや水辺環境の大切さを知ってもらうことを目的に、初めて開催されました。小学校では、総合学習で笛吹川をテーマに調べ学習に取り組みながら本日を迎えました。

アユは1年しか生きられず、秋に孵化して海に向かいプランクトンを食べて過ごし、春に川を上って水生昆虫を食べ大きくなります。
大人になると苔を食べ、なわばりを持ち、なわばりの中に他の魚が入ってくると体当たりをします。
秋に産卵期を迎え一生を終えます。(中には、もう一年生きる長寿のアユもいるそうです。)
アユは、一年間で25cm前後まで成長し、大きなものは30cmにもなるそうです。アユは香りが良い魚で香魚とも言われています。
笛吹川のアユは、富士川で魚道が整備されておらず、海に下ることができないそうです。
夏になると川の中で、長い竿をもって釣りをしている人を見かけると思いますが、これはアユの習性を活かしたアユの友釣りをしている人の姿です。
もう一つ、笛吹川の夏の風物詩と言えば、「鵜飼」です。鵜を使ってアユ漁を行う伝統的な漁法です。鵜飼いを見た際には、今日放したアユのことなど思い出してもらえたらうれしいですと子どもたちに伝えてくれました。

子どもたちは、今回の貴重な体験を通して、笛吹川のアユの過ごしやすい環境について考えることや、釣りの楽しさを知るきっかけになったと思います。
そして、何より学校・行政・地域(今回は、日本釣振興会)の連携により、「子どもたちに豊かな心を醸成する」取り組みがされていることを知りうれしく思いました。
日本釣振興会は、魚の保護、増殖、釣り場環境整備保全、釣りに関する知識の普及などを目的に「放流事業」「水辺環境美化保全事業」「釣教育・釣振興事業」「釣りマナーと安全対策の啓発事業」等を行っています。
日本釣振興会山梨支部の支部長を務める雨宮さんは、鵜飼橋のたもとで釣具店を営みながら、主任児童員として、また地域福祉推進委員会の世代間交流グループのメンバーとして、誰もが安心して暮らせる地域を目指して、より良い関係づくりを広めています。
ブログをご覧の皆さんのお住まいの地域では、どんな取り組みをしていますか?
ぜひ、ちょっとしたことでも大歓迎です。皆さんのお住まいの地域の様子を教えてくださいね。
つなげよう、つたえていこう、温かい心、いさわ
支え合う地域づくり 石和 石和地域事務所 萩原
こまめに「うがい・手洗い」、「3つの密」を避けるように意識して、新型コロナウィルスの感染拡大防止に努めましょう!