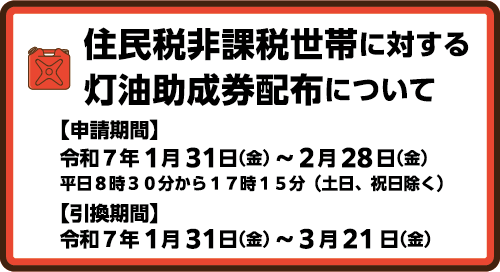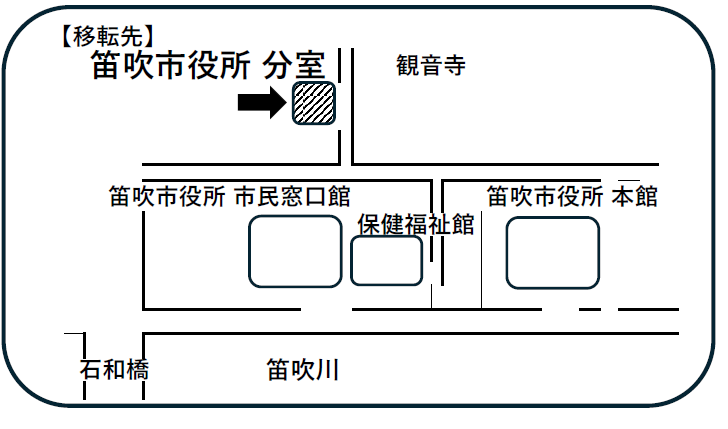皆さん、こんにちは!山梨県立大学、実習生の近藤尚崇です。




社会福祉士になるために、笛吹社協の石和地域事務所で、24日間に渡り実習をさせていただきました!
私は、この実習の目的を「地域住民一人ひとりが主役となれ、『住みやすい、暮らしやすい』と感じる地域になるために、社会福祉協議会がすることの出来る、人・環境への曖昧さの無い『支援』とは何か?」というところに置き、取り組んで参りました。
社協が住民や地域に対してやっていることは何なのか?大学で学んできたソーシャルワークの「価値・知識・技術」が、実際の現場ではどのように実践されているのか?などの疑問を解き明かすべく、そして、「そもそも『支援』って何!」と自分の中のフワフワした感覚を少しでも形あるものにしようと、様々な経験を通し学びを深めてきました。
コロナ真っ只中ではありましたが、オンラインでの各事務所へのインタビュー調査の実施や、生活支援コーディネーターの情報交換会への参加をはじめ、「支援センターふえふき」では初めてのデイケア体験ができ、「日常生活自立支援制度」の同行訪問、推進委員会の会議参列、後見申立の面談同行、個別支援の面接や地域支援の聴き取りなど、多くの社協職員さん、地域住民さんに支えられながら何とかやって来ることができました!
地域住民の生の声を聴けたこと、現場でのソーシャルワークを目で見て、実際にやってみることができたこと、ここでの学びを今度は大学へ持ち帰り、更に深く考えていこうと思います。
↑...実習前に参加した駅前花壇の環境整備ボランティア(運営側)の活動。
蔓延防止措置により住民活動への参加がほとんどできなくなってしまった中、実習前であったこの活動に参加していて良かったと思います。多くの地域住民さんが参加されていて驚きました!
↑...権利擁護について職員さんから説明を受けている様子。
日自の同行訪問や家裁への申立などを通し、「自己決定の尊重」や「最善の利益」について多くを学べました!
↑...デイケアで作品の作成もしました。
これらの作品は過去のものになりますが、今年の出品作品を一緒につくることができたのはとても貴重な経験となりました。障がいへの理解がもっともっと深まることを心より願っています。
↑...実習最終日の発表の様子。
個別支援を通し、地域の課題の発見ができました!解決の仕方は模索しましたが、そんなに簡単な話でもなく、地域福祉活動計画の評価や強化、地域住民一人ひとりへの働きかけなどの重要性を認めてもらえたと思います。
約1ヵ月の実習を通し、地域の皆さんと社協との繋がり、安心して生活できる地域について多くを学ぶことができました。
社会福祉士として、どのようなはたらきがけをするべきなのか、どのような支援が支援たるのか、実習での学びを糧に、今後更に考えを深めていこうと思います!
協力していただいた皆様、本当にありがとうございました!
こんなまちであったらいいな
安心して暮らせる幸せあふれるまちづくり
つなげよう、つたえていこう、温かい心、いさわ
山梨県立大学 実習生 近藤