支援センターふえふきが主催する、地域啓発研修「ヤングケアラーって何?」が10月4日に開催され、無事終了しました。参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、心より感謝いたします。
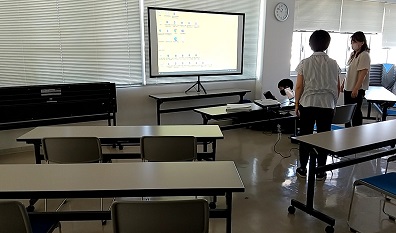

参加についてはオンライン研修ではありましたが、オンライン環境が無い方や、使うことが難しい方には集合会場として、市役所市民窓口館302号室をサテライト会場として用意していただきました。ここには基幹相談支援センター職員が常駐して、中継をしていただきました。
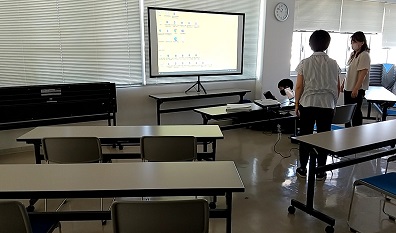
研修は、定時の13時半にスタート。まずは当社協の竹内会長から開会の挨拶を、続いて笛吹市福祉総務課・笛吹市基幹相談支援センター新開課長様より、挨拶をいただきました。お忙しい中会場に駆けつけていただき、ありがとうございました。
研修ですが、まずは山梨県が行ったヤングケアラー調査の結果を、県障害福祉課の地場さんより説明をしていただきました。そして、白梅学園大学の森山教授からの講義となりました。森山先生からは、小平市の調査に参加した時の結果や、実際のケアラーの映像等を交え、ケアラー本人が何をしてもらいたいかなどの発表をしていただきました。

参加者ですが、サテライト会場含めて約70名ほどの参加がありました。オンラインの利点を生かし、北杜市や大月など遠方からも参加もありました。
質疑応答やアンケートでは、実際にどのような支援が出来るのか、その体制はどうするのか等の質問がありました。必要な支援体制を考えるのも大事ですが、山梨県でもようやく実態調査が始まったばかりです。国でも専門機関を立ち上げ、今後に対応を考えていくとのことです。
さて、「浮浪雲」(ジョージ秋山著)と言う漫画があります。その中に、小さな男の子が、道に落ちているタバコをこっそりと拾い集めるお話があります。旅人がその男の子にどうするのか聞くと、「寝たきりで病気の父親に吸わせてあげたい・・・」と言う。すると旅人はタバコを与え、「苦労は薬にも毒にもなる。辛抱なさい」と去っていきます。
さて、この場合の「薬」に代わることはなんでしょうか。病気の父親を診てあげたいという男の子の気持ちを理解し、応援し、手を差し伸べること。
では、「毒」になってしまうことはなんでしょうか。それは、無視をすること。押し付けること。そんな子どもは居ないと無関心になることではないでしょうか。同じ辛抱するにも、結果は違ってくるのではないでしょうか。
森山教授が紹介したヤングケアラーの訴えにもあったように、まずは声を掛けてくれて、認めてくれたこと、話を聞いてくれたこと、がとてもうれしかったと言っています。
この研修のゴールは、参加者が、ヤングケアラーとなっている子どもや、もしかしてヤングケアラーではないかと思われる子どもが居た時に、その子に「あなたも大丈夫?」と声を掛けることが出来るようになる、と想定しました。
皆が無関心にならず、また過度なケアを押し付けず、子どものケアをしてあげたいという気持ちを大事にしつつ、その将来の姿も見守れるような共生社会づくりが、今求められています。














