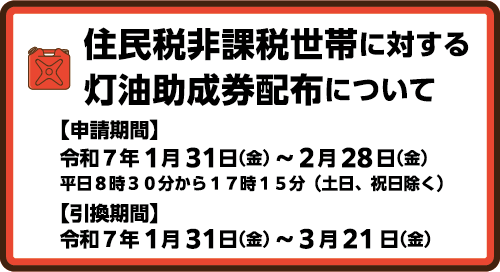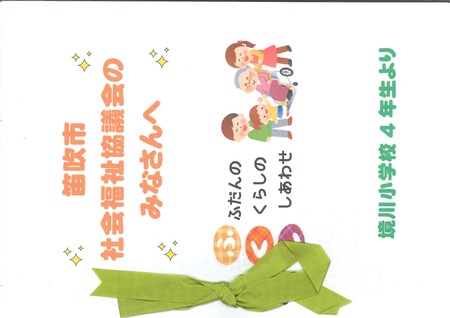これまで県地震防災訓練の中で行われた災害ボランティアセンター設置運営訓練への参加の様子をシリーズ1・2・3にわたりお届けしてきました。
今回はその後行われた反省会について様子をお届けします![]()
12月15日、訓練から1か月経過したところで、
訓練に参加された皆さんにお集まりいただき、振り返りをおこないました。

参加したそれぞれの活動について、
『災害時のボランティア役』として参加した障がい当事者のお二人からは...
*ボラセン受付では、受付票を書くのに短時間で正確に書くことが求められたり、
受付スタッフのピリピリ感が伝わってきて緊張した。もっと書きやすいような
配慮があると良い。
*ボランティア先で行った段ボールベッド作りは、いい経験・勉強になったけど、
障がいで片手しか使えないので、折り目をつけるしかできなかった。
*障がいで片手しか使えなくても、もっとできることがあったんじゃないかな。
*福祉避難所と一般避難所の違いや、ボランティアとしてどんなことに
気をつけたらいいか分かったらもっとよかった。
*ボランティアを含め協働する方々がどの程度障がいへの理解があるのか、
まずお互いを知ることが大事だと思う。
『ボランティアセンターのマッチング役・事前オリエンテーション担当役』
をされたボランティアのお二人からは...
*事前の打ち合わせや感染症対策など、課題はあったが笛吹市で行う際には
さらにより良い方法を考えたい。
*災害救援ボランティアセンター設置運営マニュアルは誰が見ても分かるように
なっていること、行政と連携し検証していくことが必要である。
*訓練は毎年、避難所も想定して行うことが大切。
*笛吹市での防災訓練でも、障がい者の方にも協力してもらいながら取り組んで
いきたい。障がいがある方にしかできないこともある。
...との感想が聞かれました。
障害にも目を向けた災害ボラセンの設置運営について継続的に考えていこうと共有できたことや、笛吹市での災害時の体制、地域共生について考える機会となりました。

有事の際のことを考えると、避難所に「避難できてよかった」ではなく、避難した先のことも考えなくてはなりません。
避難所生活では情報がうまく得られずに不安な気持ちや孤立してしまうことも予測できます。ボランティア活動への参加など、「つながる」ことが心の安定にも結び付くと言われています。
障がい者が助けられるだけの一方的な関係ではなく、障害の有無に関わらず、支え支えられのお互い様の関係づくりが出来ると良いですね![]()
![]()
社協では今後も継続的に、地域の皆さんの生の声を聞き、生かしながら
防災の取り組みや障がいについての地域啓発に取り組んでいきます![]()