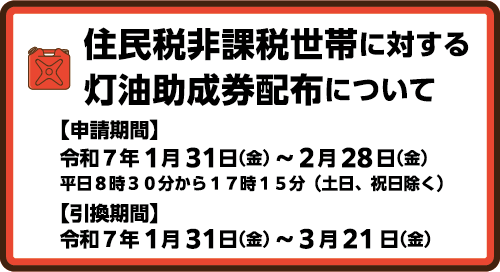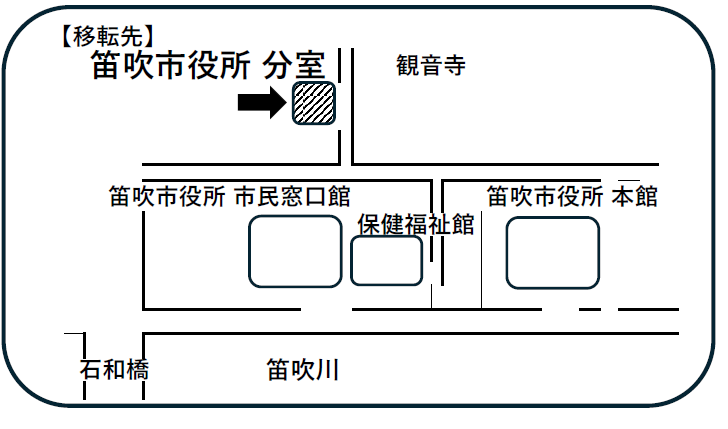「地域福祉推進委員さんてどんなことしているの?」をテーマに石和地域の推進委員の皆さんにお話を伺いました。
※誰もが安心してくらせる地域を作るために、地域住民の皆さんが行う内容を示した地域福祉活動計画が作られています。この計画に基づき、住民の皆さんが住みよい地域を作るための活動を中心になって行っていくのが 地域福祉推進委員会です。
今回は地域福祉推進委員会の活動の一つ「支え合う地域づくりいさわ」について、代表の安藤さんと副代表の伊藤さんに活動の様子を伺いました。
※「支え合う地域づくりいさわ」とは笛吹市石和町の生活支援体制整備事業・第2層協議体の愛称です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように町内の実情に合った「住民同士の支え合い・助け合いの地域づくり」を推進している活動です。地域福祉推進委員会の活動の一環として行われています。

インタビューに答える伊藤さん(右)と安藤さん(左)
社協:お二人は、どんなことがきっかけで推進委員へ就任されたのでしょうか?
安藤:スコレー大学(笛吹市の市民講座)で防災のことを勉強し、なにかこの学びを生かす機会がないかなと考えていたところに区長さんからやってみないかと話がありました。
伊藤:「居場所づくり」の活動で市の第一層協議体委員になったことから、第二層協議体「支え合う地域づくり石和」の委員もすることになりました。そして二層の委員になったら、もれなく地域福祉推進委員もくっついてきた・・・おかげでいままでなかなかお会いする機会がなかった、近隣他区の方々と出会えたり、推進委員の活動そのものも知ることができました。
社協:安藤さんは推進委員になってからは、認知症サポーターでの活躍、ボランティアで地域の方の困りごとの支援に関わっていますね。
安藤:自分のできることは積極的にやりたい、という思いがあります。当初、高齢者の自宅にカーテンを取り付けるというボランティアの依頼だったのが、その方が認知症で実際に関わってみると目の前の困りごとだけでない家族との関わりの大変さがあったり、ひとり暮らしの方の自宅に溜まってしまったゴミを片付けたけれど、そもそもそんな状況になった元の部分に関わることができないとまたゴミが増え始めてしまったり...色々な課題があると肌で感じています。
認知症サポーターの活動は、学校や地域の高齢者サロンなどで行っています。子どもたちには、これからますます増えていく高齢者を理解するツールの一つとして、高齢者自身であっても認知症そのものへの学習の機会は必要だと感じています。

中学生に認知症サポーターの講義をする安藤さん
社協:伊藤さんの普段の活動についても教えて下さい。
伊藤:生活弱者になりやすい、女性、子ども、高齢者に向けた活動がメインです。「支え合う地域づくり」としては、コロナの影響で、居場所づくり活動ができなくなっていることと、意外に進まない市民の理解に、第一層協議会の広報委員として、「どうしたら活動を理解し、担い手となる市民を増やすことができるか」に頭を悩ませています。

支え合う地域づくり石和の中でのグループ会議で意見を述べる伊藤さん(右端)。
社協:支え合う地域づくりの活動はいかがですか?
伊藤:「支え合う地域づくり石和」は、近所のつながりが希薄化する中で、主に高齢者の困りごとなどを「地域の助け合い」で解決することができるような仕組みやしかけを考える活動ですが、「地域福祉推進委員」は、それを自らが実践することが活動なのだと思います。
安藤:高齢者の移動支援が大きな課題と感じています。地域差もありますが、私の住む地区では自動車に乗れないとゴミ出しや買い物に途端に困ってしまいます。色々課題はありますが、例えば地域での仲間で一緒にゴミ出しを支援するグループなどを作っていけるようにしたいですね。
社協:地域の皆さんにメッセージをお願いします。
安藤:地域で新しい取組を始めるのは大変ですが、今までおこなっていた活動を「そもそもなぜそれを行っていたのか?」を振り返り、より良い形に、より発展していく形でできたらいいと考えています。
地区で様々な役割を引き受けることに、難しさや責任を感じることもあると思いますが、1年で終わってしまうのではなく、数年関わっていくことでよりよく、よりやりやすくなっていくと思います。なので一度何かの活動に関わったら継続して関わってもらえると嬉しいですね。
伊藤:広報委員として「今は元気。いつまで元気? いつかはきっと自分ごと。」というキャッチコピーを考えたのですが、これがもっと広まらないかな、と思っています。でも本当は「自分ごと」になる前に、気がついてほしいし、出会ってほしい。
人と関わることはたいへんで、ときには傷つくこともあるけれど、共に生きる人生は、豊かで楽しいものです。
誰かのために、は自分のためでもある。よりよく生きる、ですね。