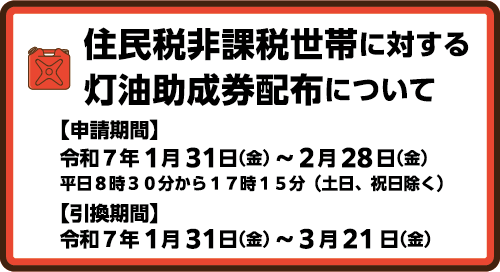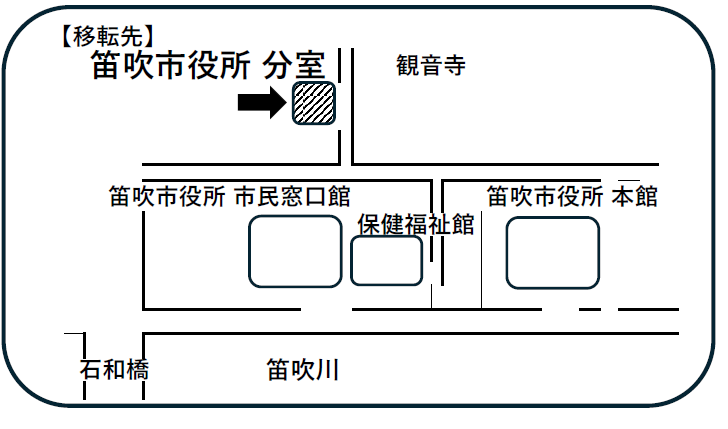「地域福祉推進委員さんてどんなことしているの?」をテーマに石和地域の推進委員の皆さんにお話を伺いました。
※誰もが安心してくらせる地域を作るために、地域住民の皆さんが行う内容を示した地域福祉活動計画が作られています。この計画に基づき、住民の皆さんが住みよい地域を作るための活動を中心になって行っていくのが 地域福祉推進委員会です。
今回は「防災グループ」の小俣さん、雨宮さん、野田さんからお話を伺いました。
社協:地域福祉推進委員会に参加することになったきっかけを教えて下さい。
小俣:数年前に区長を務めた時に、自分の地域の推進委員が決まっていなかったため引き受けたのが始まりです。区長は退任しましたが、推進委員活動が区の中で認知度が低く、活動をスムーズに次の人に引き渡すことが大変難しいと感じる引継ぎ方法を模索しています。

インタビューに答える小俣さん
雨宮:数年前に区長だった時に、大雨で近くの川が決壊するかもしれないということがありました。地区の皆さんから問い合わせがありましたが、いざとなると誰にどのように避難の情報を伝えて、どんなタイミングで避難すればいいのか、の難しさを感じました。要援護者としての名簿はあっても避難の際に区として誰が支援が必要なのかが明確に分からず、そういったことも知りたいと思って推進委員会に参加するようになりました。
野田:私も同じ時に区の役員をしていました。当初の避難所へ避難することが難しいということで、近くの商業施設や公共施設への避難場所を切り替えられないかを雨宮さんと一緒に交渉したりしました。雨宮さんとは民生児童委員にも同時に就任したので、その関係で防災グループでの活動に加わっています。

インタビューに答える雨宮さん(左)と野田さん(右)
社協:防災グループではどのような活動をされていますか。
小俣:市の防災危機管理課の方を招いた防災学習会を年に何度か開催しています。コロナの前には地域の高齢者サロンや介護予防事業へ行き、防災啓発活動をしていました。
野田:私や雨宮さんは推進委員会に加わったのがほとんどコロナ禍の時期になっているので、委員の活動として対外的なところへ出ていく機会はまだないのですが、防災学習会では一住民としても知らなかったことがたくさんあるため、本当に学ばせてもらっています。
社協:皆さんは日頃地域でどのような活動を行っているか教えて下さい。
雨宮:民生委員として地域の気になる方への訪問をしています。ただ、アパートが多い地区で自治会への登録が少なく、実態を把握することが難しいなと感じています。
野田:私も民生委員として実際に訪問しますが、色々な訴えを受けています。すべてを自分一人で対応するのは難しいですので、ご本人だけでなく、近所の方からの間接的な役割を含めて関わっていかなければならないなと思っています。

小学校区毎の地域での防災の話合いの様子
小俣:昨年の春から自主防災の組織を自分の地区で立ち上げました。地区の皆さんに防災の意識を持ってもらえるような活動や、組織が継続的に続けられる仕組みづくりを考えながら進めています。
社協:今後の活動でこうしていきたい、と思うことがありましたら教えて下さい
雨宮:地区でのグランドゴルフや生け花などの集まりがあるので、そういった機会を利用して、皆さんに防災など知ってもらいたいことを伝えていきたいです。
野田:自分の住む地区は高齢者でアパートに住んでいる方が多く、関わり合いが少ないです。防災は個々が色々な場面を想定した中で「どの様な柔軟な対応が必要なのか?どのような意識でどの様な行動をとらなければならないのか?」など広く考えていかなければならない時期に来ていると思います。そういった意識にそれぞれの個人が変わっていくように地域で関われたらと思っています。やはりコロナが落ち着いたらみんなと話をしたいですね。
小俣:自分の地区で高齢者が集まるコミュニティが無くなってしまっているので、少人数でもそういうものがいくつかまた作れるようになれたらと思っています。
高齢者に限定せずに若い世代からの集まりで勉強会を開いたり、地区の行事の文化祭、運動会に「防災」に関わることも取り入れていけたらと思っています。
私の地域は他の地域と同様に高齢化が進んでいます。アパートに住んでいる人たちも多く、地区で情報発信がしづらいと感じることもありますが、コロナが収束して世代間交流が地区の中できるようになれば、防災だけでなく色々なものを伝えやすくなっていくと思います。

防災グループでの話し合いの様子