笛吹市自立支援協議会の相談支援部会長の鈴木です。
 、
、
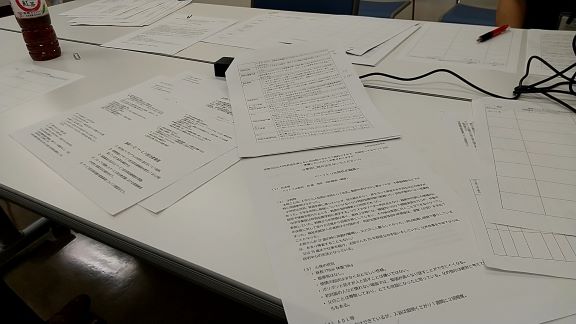
さて、8月の相談支援部会は、急遽予定を変更して、日本相談支援専門員協会が実施する、「基幹相談支援センター強化研修」を皆さんと一緒に行いました。
8月2日、14時から17時過ぎまでの3時間の講義。市役所の会議室で行いました。
この研修の目的は、市内の指定特定相談支援事業所(計画相談)の相談支援専門員の人材育成になります。これは、地域拠点事業で笛吹市が担う「人材育成のための研修」にもなっています。
具体的には、計画相談の作った計画書・モニタリングシートを基幹の主任相談支援専門員が定期的に確認出来ようにすること。また、訪問時には相談支援専門員を同行させたり、より良き形で面接技術や個別支援会議を進められるようになるということを目標としています。
まずは本的な講義の流れの説明を受け、どのような演習をするのか確認します。事例としては、高齢の親と同居する息子さん。いわゆる8050問題です。
 、
、 面接時に、相談員はどのような事を意識して面談を行っているのかを自己分析し、用紙に記入します。
次に模擬面談です。主任相談支援専門員役の人、それに同行して面接を見る相談員の人、障がい当事者の人の3つの役に別れ、模擬面談を行いました。障がい当事者さんの大まかな設定を元に、聞き取りの面接のお芝居です。
相談員にとっては、面接は日常業務です。改めてここで「形式に当てはめた面接の流れ」を提示されると、やっていない事、意識出来なかった自分の癖などが見えてきます。秘守義務は説明出来ているか、メモなどを取ることの了承はどうか等。模擬面接の終了後は、評価を全員で行いました。
次は、模擬個別支援会議です。日本相談支援専門員協会で、先に様々なサービス事業所や支援者が入った会議の様子を録画したものを、一斉に配信します。画面上では、その当事者さんの生活が変わるような出来事があり、様々なサービスを使用することになりました、が、会議は大混乱。それは・・・
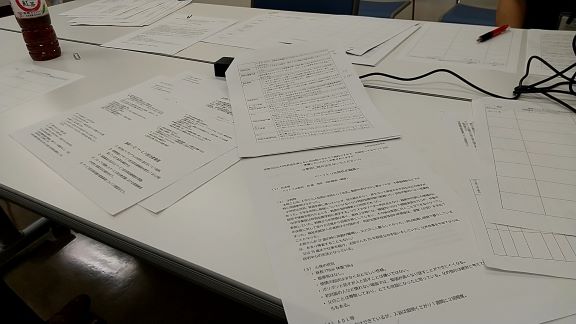
という進行に沿って、皆で動画を見て、どのような会議だったかを話し合います。正直、これほど問題の多い会議を本当に開くのでしょうか。
でも、こうやって改めて問題の多い会議を見せられ考えました。無意識に私たちも同じことをしているのかもしれません。当事者本人の事を無視した流れや、「本人にとって良いと思うこと」を押し付けてしまっているとか。危険を理由に誰かの管理下に置かなければとか。
こういうことの意見を出し合った後で、ではどのようにしたら良いのかを話し合いました。
時間にして3時間の研修でしたが、あっという間に終わってしまったという感覚です。それほど難しい話では無いのですが、改めて自分達が出来ていること、また気が付いていないことを言語化した時間でした。
これから、基幹や主任相談支援専門員の役割としては、圏域内の相談支援専門員を指導する、ということが求められています。そのためには「形」を示すだけではなく、なぜそのような「形」を行う必要があるのかまで教授することが必要です。そのためには、日常的に自分達の仕事を言語化し、いつでも、だれにでも言葉にして教えることが出来るようにしていきましょうという講師の言葉で終わりとなりました。
ちなみに、鈴木も笛吹市からの委託を請けた委託相談支援事業所の主任相談支援専門員です。基幹相談支援センターと一緒になって、こういった研修や事業を行っています。
※日本相談支援専門員協会とは・・
相談援専門員は、障害児・者等(以下、利用者※とする)が自ら望む自立した地域生活の実現に向けて、本人の意思、人格ならびに最善の利益を尊重し、常に本人の立場に立ち、個別生活支援と地域づくりを両輪とした相談支援を実践するソーシャルワーク専門職 とあり、障がいの方々が各種福祉サービスを受給する際の調整だけではなく、様々な相談支援を行う職種です。教会は、その専門職集団として、国への提言や各種研修などを行っています。
また、山梨県にも、相談支援専門員等が所属する相談支援ネットワークやまなしがあります。
他市では、この相談支援の事業を基幹相談支援センターと、指定特定相談支援事業所(計画相談)だけで行うところもありますが、笛吹市は、市直営の幹相談支援センターを設置し、市内の4か所の委託相談支援事業所に相談業務を依頼してくという方式を取っています。国では「主任相談支援専門員」を基幹に配置するとしていますが、笛吹市は委託相談支援事業所に主任を置くことで、相談支援体制を構築しています。














