8月28日の9時30分から、春日居あぐりステーションにて、令和5年度第一回笛吹市発達障害支援関係機関連絡会議に参加しました。
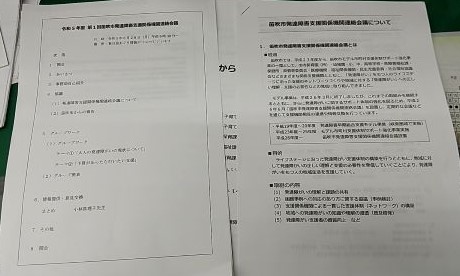
発達障害は2005年から施行された「発達障害支援法」の中で規定されたものであり、最近その数が増え続けています。発達障害は脳に起因する障がいで、治療で治る、というものでは無いのですが、幼少期からの適切な支援を受けることにより、より安定した生活を送ることが分かってきました。障がいでも人によるさがとても大きく、大きな問題も無く普通に過ごす事の出来る人も居れば、その分かりにくさ故に周りからの配慮を受けにくく、生きにくさを感じてしまう人もいます。
笛吹市では2011年からのモデル事業から取り組み、モデル事業終了後もこの関係機関連絡会議と形を変えて、年間を通じて様々な取組をしています。
支援センターはこの事業を協働する運営委員として参加しています。
この日は、市内の様々な機関の方が集まり、この会議の意味合いから、笛吹市の各機関からの現状報告を受けました。発達障害は、幼少期に発見される場合や、社会人になってからの生き辛さを訴える中で発見される場合など、様々です。
発表も、義務教育以前の環境の中での発達障害と診断された数や対応、それからライフステージにおいての様々な支援の場からと、流れの中での支援の現状の発表でした。発達障害と診断される人は増えているだけではなく、特に個別の対応を必要としている人も増えており、教育の現場でも対応に苦心んしていることが伺えます。
子育て期、義務教育期、成人期などの支援機関から情報提供でした。
次は支援者によるグループワークを行いました。2つのテーマを元に、KJ法、ワールドカフェを使ったワークにて協議をしました。
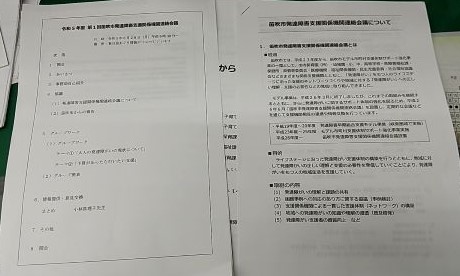
最後には、山梨英和大学教授の小林真理子先生から、今日の会議の講評を聞きました。
今年度は後期に向けて、普及啓発の研修をしたり、支援者向けのスキルアップ研修会を開催する予定です。














