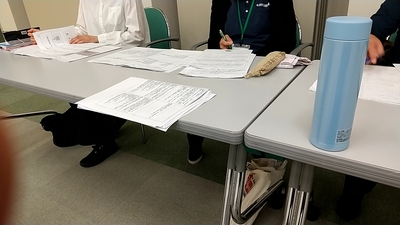自立支援協議会は、障がい者に関する総合支援法の中に規定された協議会です。笛吹市内の福祉関係者、関係行政職員、福祉サービスの事業所、家族や当事者、地域住民などの代表者が集い、市内の障がい福祉に関わる様々なことを協議する場として設置されています。基幹相談支援センターが主催となっています。
10月9日、9時30分より、春日居のあぐりにて、自立支援協議会は開催されました。これは年に3回実施され、年間の活動計画、中間報告、年度末の報告などの機会を設けます。
主の活動は部会単位で行われているので、部会の活動報告と、その他事業の報告、市の障がい福祉の関わる報告などを行い、協議を重ねています。
ジチョーは、相談支援部会の部会長なので、前期(4月から9月)の活動を発表しました。事例検討会と、当事者が参加してのアセスメント演習、国が進めているモニタリング検証のデモです。
内容は、社協ブログにも挙げていますので代表的な活動をご覧ください。
各部会での発表からの質問では、市内のグループホームについての話題が出されました。今年度、新しくグループホームが市内にも出来たこと、また長期入院している方や、施設入所されている方のグループホームへの移行が増えていくことから、グループホームへの意識は高まっている一方で、重度障害の方が利用できる状況にあるのかなどの質問がありました。
さて、今回は防災についての現状と言うことで、支援センターの防災に関する活動を通して見えてきた課題などを発表しました。大事なポイントは「共生社会」「協働」です。
支援センターは社協活動のひとつの部所でもあります。社協の地域福祉の推進の一端を担う部署でもあるので、地域の皆さんの意向を意識した活動を展開しています。
さて、今回視聴者として相談支援専門員の現任研修を受講されている4名が参加しています。この研修の科目の一つに、「自立支援協議会の活動を知る」という項目があることを受け、参加が出来るようにお願いしました。
初めて協議会に参加する相談員ばかりで、「こんなにも市内の福祉に関わる重要な方が集まる場だと初めて知った。でも、この協議会で話された内容は、今後どのように県や国に伝わり、制度改革などの具体的な成果に繋がるのか」等とても厳しい意見質問が出ました。
ジチョーも委員として発言(この日も恐らく発言量の7割がジチョーだったのではないか)している責任を、改めて感じています。