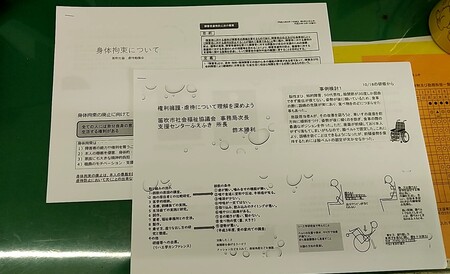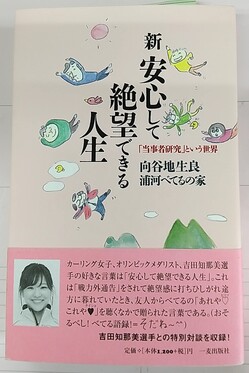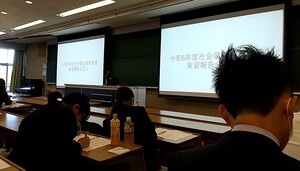ジチョーです。
2月になっても、時間を作っては色々と歩いております。
1,セーフティネット勉強会
2月4日、峡東保健所主催の会議です。オンラインを使っての会議でした。まずは県内の自殺(自死と表現することも増えました)の数値の報告。数は減ってきていますが、相変わらず若い人の自殺が多く、令和4年度よりも514人の児童生徒が死を選んでしまっています。
今回はそれらを含めた児童精神科での様子を学びました。国府台病院は児童精神科病棟があり、入院される児童の対応をしているソーシャルワーカーから説明を受けました。児童精神科病棟はまだまだ少ないのが現状です。
2,朗読ボランティア発表会
2月9日の日曜日、朗読ボランティアの皆さんの発表会があり、お手伝いをしてきました。
朗読ボランティアの皆さんには、支援センターふえふきの事業のひとつの「声の広報」作成を依頼しています。毎年、朗読奉仕員養成講座を卒業された方々の活動先として、サークル活動を紹介しています。この発表会は朗読発動をされているサークルの方々の発表会となっています。
支援センターふえふきは、ボランティア活動支援の一環として活動支援をしており、この日も当会の竹内会長が開会の挨拶と詩の朗読を披露。担当職員の小林も事前準備からお手伝いに入っています。
今年も、ジチョーは飛び入り参加をさせていただきました。サークルの皆さんと一緒に今後も発表会を盛り上げていきましょう。
3,法人内虐待研修を開催
福祉施設では、虐待を防止する対策として、年に1回以上、職員は虐待と身体拘束の研修をそれぞれ受けることと義務化になっています。当法人の職員は、全員何かしらの機会で、研修を受けています。
今回は身体拘束の研修会を開催しました。虐待を学ぶ場は増えていますが、身体拘束の研修会はまだまだ少なく、特に障がいの事例に従った研修は少ないのが現状です。
2月10日、17時より、スマイルいちのみやで、講師はジチョーが担いました。ジチョーは笛吹市自立支援協議会相談支援部会でも、年に1回は虐待の勉強会を行っていたり、国が実施した虐待対応講師養成研修も受講しています。
今回は2つの事例を基に検討しました。ひとつは、強度行動障害の方が道に飛び出してしまう場合、職員が抱き留めて飛び出しを防いだが、これは身体拘束に当たるか。もう一つは車いすのベルトを作成し、車いすから落ちないようにしたがこのベルトは身体拘束になるのかという事例です。いずれも身体拘束に当たる行為ですが、では何も手を出さないままで良いのか、というのは違います。身体拘束にしない取り組みを基に、職員は何をすればいいかを職員で討議をしました。
他の事業所でも、虐待についての研修、身体拘束での研修を企画したいという場合は、対応しますのでご相談下さい。ジチョーが資料を持って参じます。
この後にも、2月には様々な会議などがありますので、順次お知らせをします。










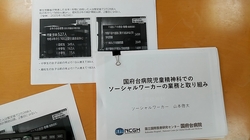
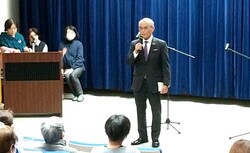


-thumb-250x140-22293.jpg)