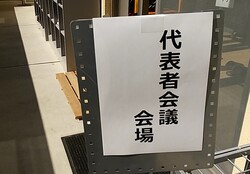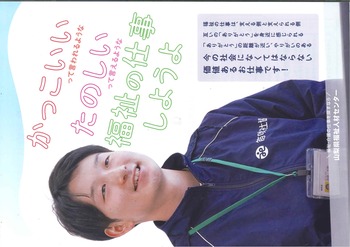ジチョーです。
今日は4月1日と、新しい年度がスタートしています。各課には新しい職員も増えています。同時に離れていく人も居て。様々な出会いがありますので、是非お声をお掛け下さい。
さて、3月後半の様子をお伝えします。
〇3月15日 13時30分から 八代総合会館
八代の「いまのこまりごととこれから」学習会
八代の住民さんが集まって、八代のこれからを話し合うばとして、住民の皆さんが集う場としての学習会に参加しました。今回も社協職員を中心にお伝えします。
八代福祉推進委員長の今泉さん、支え合う地域づくり会議からは佐々木さんが会の進行や意味合いなどを提供し、5から6名がひとつのグループとなって、今の自分たちの生活の困りごとを中心に話し合いました。例えば移動の問題であるとか、地元商店が少なくなって買い物にも支障があるとか。
例えば。八代にも「のるーと」が走っていますが、実際に利用される方は少ない。では、なぜ利用しないのか。
「バス停が近かったら、もしかしたらもっと利用するかも。」という方がいて、こういった相談は社協で解決するのか。
成程、社協の相談機能をもっと充実せねばと危機感をもったジチョーでした。ちなみに相談は答えを出すか否かではありません。整理し、切り分けて依頼していく。こういう手法を職員は学ばねばなりません。
最後に、県社協の和田課長から、社協に期待されることをテーマに話がありました。
しかし、住民さんのパワーが凄い。小雨の肌寒い中、パワーはしっかりと伝わってきました。
〇3月22日 14時から17時まで。植草学園大学 野澤和弘教授他。オンライン。
「強度行動障害のある人の
豊かな地域生活を実現する『地域共生モデル』の理論の構築と重層的な支援手法の開発のための研究」と、長い名前の研究の成果を聞くチャンスがありました。
強度行動障害のある方の中には、感情と状況の不一致で激しい行動になってしまったり、突発的な骨導に繋がってしまう障がい特性の方がいます。道を歩いていても、道路に飛び出してしまうなどもあり、安全のための支援が特に必要なこともあります。でも、その特異な行動も、実は意味を持った行動であることも多く、意思疎通が取れないわけでは無いのです。
今や、色々な障がいの方々は人口の1割は居る、と言うことが明確になっています。以前は障がいは隠すもの、だったかもしれませんが、今は全ての人が同じ社会に生きることをお互いに意識しましょうという「共生社会」が主になっています。皆さんも、どうか自分の周りにも「強度構想障がいの方々は居る」ことを意識しましょう。
〇中央市社会福祉協議会のイベントに参加しました。 3月23日
他市の社協さんはどのような活動をしているのか、ということで、お休みの日に行って様子を見てきました。社協が入っている建物の駐車場には多くの出店があり、住民主体のお祭りをしています。目立つのはキッチンカーなどの本格的なアジア料理。そして福祉作業所のお店、地元農家のお店もあります。
中央市の事務局長さんに案内していただいたところは、学生さんが多く参加しているブースでした。子ども向けイベントとしてのブースを、学生さんに企画運営を任せて定例で行っているとのこと。学生の内に住民参加型のイベントを体感できるのはとても有利です。中央市に若い人が多くいるのも分かりますね。
中央市は人口規模で言えば笛吹市の半分。それでも大勢の方が集まっていました。
せっかくなので、イマドキのアジア料理、バインミーを食べてきました。
中央市社協の皆さん、お邪魔しました。
等々。他にもまだまだ紹介したい内容はありますが、それはまたの機会に。ジチョーでした。